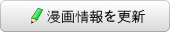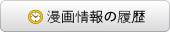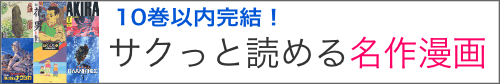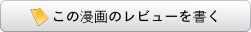うしおととらのレビュー
8点 ヒデリウさん
この漫画貸してくれた友達に感謝!
全部自分で買いなおし宝物です。
始めはグズグズ、うしおはウザいけど後半の盛り上がりが神!
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2014-09-03 23:34:13] [修正:2014-09-03 23:34:13] [このレビューのURL]
9点 paranaさん
この作品を簡単に言うなら
バトル物少年マンガの熱気を竜巻のようにまとい、
作者によってキャラクターの一人一人がこの上なく大事にされている作品。
一度登場したキャラクターが再登場して活躍していく様子は
仲間をつくることの大切さが伝わってくるし、
主人公の熱さと仲間の思いが涙腺を刺激し泣かせてくれます。
結構なピンチを用意しているストーリーにはハラハラしたし
ラスボスの白面の者の絶望的な強さというのも良く描かれていたし
特に思いっきり風呂敷広げたストーリーをラストバトルで集束させて行く様は圧巻でした。
個人的にはうしおは、獣の槍の力によって強くなっていくのではなく
(周りのキャラに戦闘のコツを少し教えて貰うシーンはありましたが)
ラストバトルに備えてもっと自分を鍛えるような場面があった方がよかったように思います。
(この辺がジャンプマンガとの違いか?)
とはいえ、うしおととらがバトル物少年マンガの屈指の名作であることは否定できません。
(泣ける度5★★★★★)
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2014-08-02 13:56:39] [修正:2014-09-24 00:13:13] [このレビューのURL]
10点 なぶさん
もうね、大好きな作品です
描写云々とかストーリー云々とかは同志のみなさんが熱く語ってらっしゃるので割愛
自分がこの作品で強烈に思うのは作者の思いの込められ方の強さ
もうね、一話一話にこーいうことが言いたいんだ!て暑苦しいくらいにこもってんの、でもそれが嫌じゃないんだ
その全てがストレートだったからなのか、逆に心地良いくらい
作者の藤田さんは大分変わり者らしい、どっかに人物評が載ってて「主人公潮そのままみたいな人w」とかいう、単行本の濃厚なおまけページにもそれは垣間見えてる
からくりサーカスも面白いけど、あっちはなんかこ慣れた感がする、うしおととらはなんていうか全力でぶつかった、やりきった感の塊とでも言おうか…
ナイスレビュー: 1 票
[投稿:2013-12-25 17:18:01] [修正:2014-04-17 22:28:33] [このレビューのURL]
8点 gundam22vさん
超有名レベルの長編妖怪バトル漫画です。
絵柄に癖はありますが画力は高く演出が上手いのは
藤田作品の特徴だと思います。
ただ前評判聞いてないと10巻くらいまでは主人公潮の
暑苦しく青臭すぎる叫びがうっとおしい、相棒妖怪とらが
主人公を助ける態度がミエミエでわざとらしい、各地を
転々と人情妖怪退治で説教臭くグダグダとか問題点を感じました。何度か止まってしまったのが正直なところです。
しかし、中盤くらいから物語が展開、加速してそこから最終決戦は怒涛の勢いのまま綺麗に畳んだのでやはり名作だと思います。
それまでの中だるみ的な登場人物までしっかり絡めましたし。
伏線も膨大ですがちゃんと回収して、槍の文字、
お役目様の行動の意味、ラスボス
である白面こと九尾の狐やとらの正体などには驚きました。
流のような良い兄貴分キャラかとみえて主人公うしお
への逃げ的な憎悪で本気で裏切っていた、とらがどうせ
助けるのかなと思いきやしっかり殺すなど予想外の展開
など終盤のインパクトも大きかったです。
最終決戦の見事さは特筆もので、このために全ての物語は
あったというほどになっています。
ラスボスである白面こと九尾の狐は実在の伝承を絡めつつ、その狡猾さ、邪悪さ、強さは絶大であり、最初から最後まで一貫してラスボスから動かなかった点でも漫画界有数の存在感があった悪役だと思います。
個人的に序盤が本当に厳しかったのでそこは短所ですが、
それ以外は高評価されてしかるべき歴史的名作漫画だと
思います。自分同様に序盤で駄目だと思った人も我慢して
最後まで読む価値は間違いなくある作品です。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2013-09-11 01:22:06] [修正:2013-09-11 01:26:57] [このレビューのURL]
10点 yosamu88さん
少し前に読破しました。長文です。すみません。
『うしおととら』、以前より「名作漫画」として名高い作品ということは聞き及んでいましたが、正直なところ、第一巻を読んでの感想は「そこまで言うほどか?」。
絵が漫画のすべてではないことは承知しているのですが、それにしてもかなり荒いし(鬣に隈取り、縞模様というとらのデザインには凄い美学を感じましたが)、そもそも作風があまりに説教臭い。熱いというか暑苦しく、古臭い。読者の思い出補正+いくつもの作品へ影響を与えた妖怪バディものの先駆けというだけで、過剰な評価を受けているのだな……と、冷めた目付きで一巻を置きました。
今思い返せば、早急すぎる判断だったと思います(言い訳をさせてもらえるなら、余計なことを考えずに作品と触れ合える少年時代に読んでればこんなことは……!)。
おカネがもったいないし、買った分の巻数だけは読んでしまおうと、気乗りしないながらも続きに手を伸ばしてから、二巻、三巻……あれ?
エピソードが積み重ねられ、物語が動き出してゆくとともに、気づけば、荒いだけと思っていた絵から作者の思いと息遣いを感じ始め、少しずつ気持ちを掴まれていきました。そして、迷いながらも途中購入した中盤からは自分でも制御できないくらいに、読み進めてゆくスピードがどんどん加速してゆき、気づけば最終決戦へ。
……最初の巻で切らなくて、本当に良かった。
少なくとも自分にとっては、久々に、「堂々完結」という字のふさわしい、一個の少年漫画を見せてもらった気がしました。
涙もろいなどと言う自覚はなく、むしろ泣ける泣けるというような言葉に対して斜に構えてしまうような性分なのですが、比喩でなく、悔しいながら泣かされてしまった。各エピソードにも名場面が目白押しですが、最終決戦に入ってからの勢いが物凄い。中でも32巻・33巻は反則です。(また、バトル漫画の常として、一般人、いわゆるモブの人々の死亡描写が派手なのも特徴ですが、一方で、そういう「普通の人々」が、精一杯前を向いて踏ん張るシーンもきちんと描かれていていたのが印象的)
かしこぶって分析するならば、この漫画は、カタルシスを作りだすのが凄まじくうまいのだと思います。作風が合わない、面白いと思えない人も当然いるでしょう。ただし、波長が合った人、何かしら同調できる部分を見つけて読み進めることを決めた人に対しては、溜めに溜めた末の、でっかい「お返し」をくれる作品です。
最終回を読み終わった後、最後の青空のページ及び、表紙に描かれた「うしおととら」というタイトルを見ると、熱く込み上げてくるものがありました。初め見た時はヘンテコにしか見えなかったこのタイトルが、なんとこの作品に、まぎれもない「一人と一匹」の物語にふさわしいことか。
少年漫画であること――大切な言葉を真っ直ぐに伝えること――から目を背けずに、力いっぱい描き抜かれたこの作品へ、魂揺るがされた一人としての「10点」を捧げたいと思います。
*追記
個人的な好みについて言わせてもらえれば、あちこちに見られる妖怪というモチーフへの愛にニヤニヤしました。字伏や一鬼、一角、山魚など、オリジナル妖怪(山魚は読者投稿ですが)が多く、また既存の妖怪に対してもアレンジを加えてある本作ですが、少年漫画的世界観との絡ませ方、また、なまはげ伝承や「しっぺい太郎」伝説を、テーマのある短編のモチーフとして落とし込む手腕には、作者の確かなこだわりを感じました。「白面の者」の啼き声が『山海教』における九尾狐の記述+本当の願望の発露という風になっていたり、とらの異称の一つに正体不明の妖怪である「わいら」を持って来たり、『稲生物怪録』の化け物たちをこの時期に採用するなど、知識があれば唸らされる小ネタが随所にあるのも素晴らしいです。(後で知ったのですが、作者はかの妖怪研究家・多田克己の友人でもあるらしい)
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2013-08-20 03:16:39] [修正:2013-08-20 03:21:17] [このレビューのURL]
PR